勉強はお好きですか?ずっと机に座って勉強するのは飽きるし耐えられないってことありませんか?
ただ、そんな方でも飽きずに必要な勉強をこなす方法があります。
それは、インターリーブ学習法です。
今回は、「変化」がテーマの勉強法。インターリーブ学習法をご紹介します。
インターリーブ学習法とは
インターリーブ学習法とは、今やっている勉強と関連性がある別のことを、途中途中で織り交ぜながら学習していく学習法です。
英語を勉強しているのであれば、
- 30分英単語
- 30分リスニング
- 30分英文法
- 休憩
- 1〜4を繰り返す
といったような感じで、単語、リスニング、英文法と関連のある別のことをして、自分自身を飽きさせないようにするのがポイントです。
そもそもインターリーブとは
まず、インターリーブという言葉はご存じですか?調べていると
インターリーブまたはインターリービング(英: Interleaving)は計算機科学と電気通信において、データを何らかの領域(空間、時間、周波数など)で不連続な形で配置し、性能を向上させる技法を指す。
引用元:Wikipedia
とあります。元々は、コンピューターなどの性能を向上させるために使われていた言葉という事がわかります。
注目していただきたいのは「不連続な形で配置し、性能を向上させる技法」という部分です。
ここが今回の一番大事な”肝”部分になってきます。
認証心理学の分野では、勉強中に関連性はあるが違う事を混ぜることをインターリーブと言います。
この方法は今に始まった話ではなく、昔から用いられていたテクニックで音楽やスポーツをする上でよく使われていました。
スポーツでも反復的に同じ動きをしていると体の筋肉が硬くなったり、悪い癖がついてしまう恐れがあるので、短時間に区切り様々なトレーニングをするように推奨されています。
インターリーブ勉強法の効果
インターリーブ勉強法は、違う事を代わりばんこに勉強していくので、「集中がその都度途切れてしまい、学習効果があまりないのではないか?」と思うかもしれません。
しかし、違う事を勉強するメリットとして、脳が退屈しないという点があります。人間の脳は興奮状態にあると記憶力が向上するという性質を持っています。
同じ勉強を何時間もしていても脳は退屈していく一方です。なかなか新しい刺激は入ってこないでしょう。しかも、根本的に長時間集中することは人間的に不可能です。
一般的には90分が限界と言われています。
そこで変化を加えることで、脳にいい刺激となり、気分も変わるので集中して勉強できるというわけです。メリハリも付くので、それぞれの内容が鮮明に記憶されます。
具体的なやり方
では、どのようにしてインターリーブ学習法を取り入れていくのか、ご紹介いたします。
あなたが音楽家になろうとする人であれば
- 楽器の演奏1時間
- 音楽理論の理解30分
- 楽器の演奏1時間
- 休憩
- 1〜4の繰り返し
というように勉強している事とは別のことを差し込み、変化をつけることです。
一定時間ずつ区切って作業を行い、集中力の限界90分になったら長めに休憩を取るという方法がいいのではないかと思います。
同じことを長時間行うのではなく、あらかじめ予定を組んでおいて、時間が来たら次に取り組むようにすると迷う事もなくスムーズに進められると思います。
2つの気をつけるべきこと
1.あまりにも関連性が無いものを混ぜないことです。
脳に定着しづらく学習効率は低くなる恐れがあります。
例えば、数学の勉強と芸術の勉強を交互に行っても、あまり関連性は見られません。(もしかしたらあるかもしれませんが。。。)
なので、前者と何かしら関わりのあるものであることを意識して勉強するとグッドです。
2.途中で時間が来てしまったとしても、最後までやらず絶対そこでやめること
これは「ツァイガルニク効果」というものが関係しています。
「ツァイガルニク効果」とは人間は達成できた物事よりも、中断している事、達成出来なかった事の方がよく記憶に残っている。 という心理現象を指します。
つまり、無理に切りのいいところまでやらずとも、時間が来たらそこでやめていいという事です。
ツァイガルニク効果について詳しく解説しているのでこちらも併せて読んでみてください。
以上二つに気を付けて、インターリーブ学習法を実践してみてください。
まとめ
今回は【インターリーブ学習法】について解説しました。関連性のあることを代わるがわる勉強するというシンプルな勉強法です。
マンネリ化して何か新しい空気を吹き込みたいという方や、長時間集中して勉強できないという方はぜひ試してみてください。
以下の記事では、より効率を高めることが出来る「ポモドーロテクニック」について解説しているので、こちらの記事も併せて読んでみてください。
なるべく早く学習した内容を定着させたいという方は「記憶を定着!そんな時に効率のいい分散学習とは?」という効率的に物事を覚えるのに適した復習頻度について解説しているので、こちらも読んでみてください。
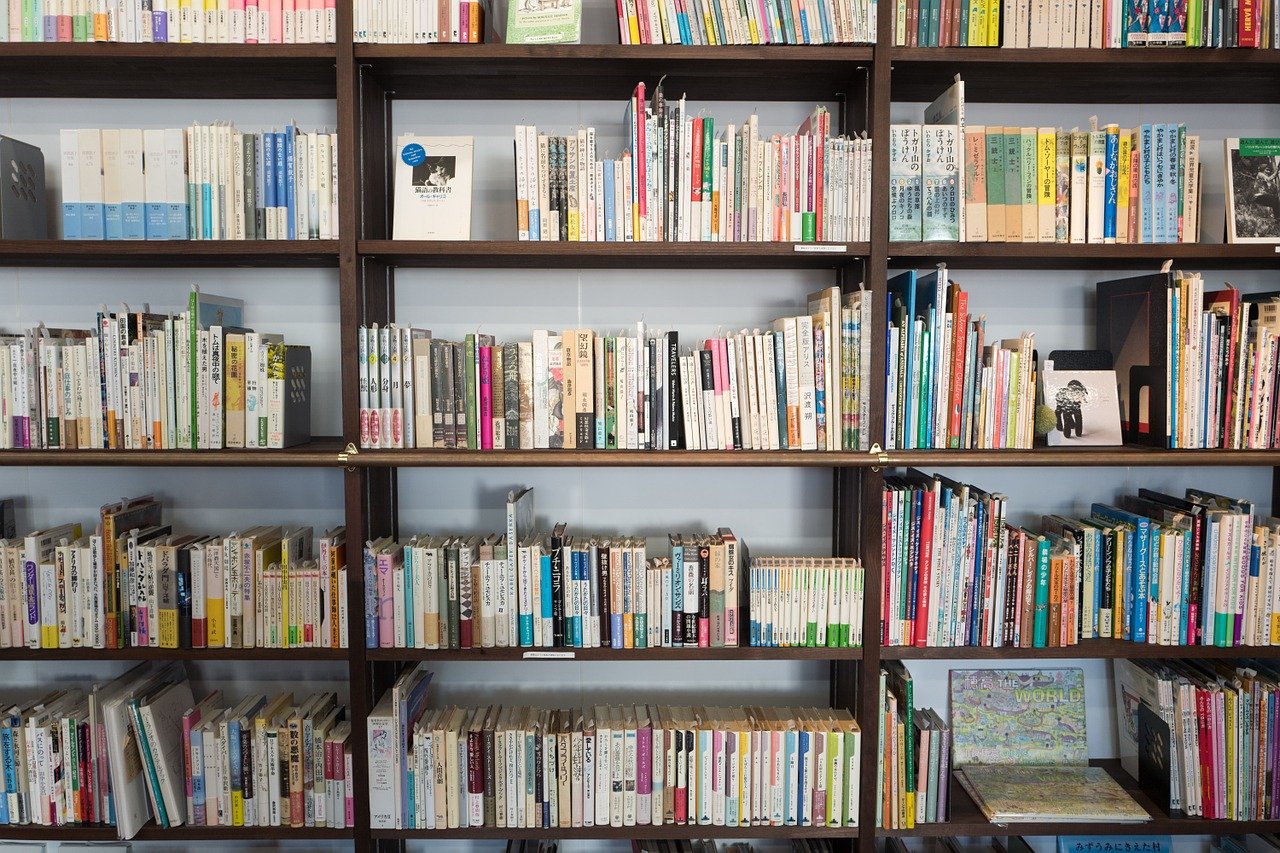





コメント